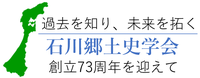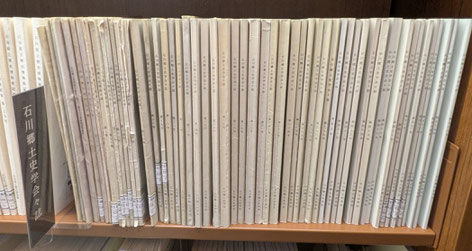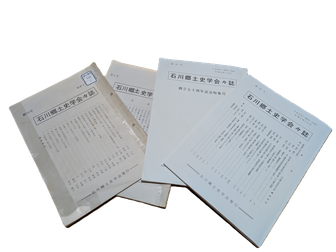学会73年の歩み
終戦から10年にも満たない昭和27(1952)年8月、石川郷土史学会は呱々の声を上げました。石川の県庁所在地・金沢は空襲を免れたものの、未曽有の国難に巷には無力感が漂い、県民は何かよりどころとなるものを求めていました。
そんな風潮に、藩政期以来、百万石の雄藩が築いてきた文化こそ、今一度再考し、戦後復興の足掛かりにしようと有志が集まったのです。活動拠点を県立図書館とし市村新館長を会長に当時の郷土史研究の第一人者であった八田健一、副田松園、殿田良作、玉井敬泉、大鋸彦太郎氏らが名を連ねました。郷土史の真実に迫り知見を共有しようとしたのが、石川郷土史学会でした。
研究域は古代から近現代まで。主な活動として、ほぼ毎月の月例研究発表会開催、当初は年2回の一般市民の参加による歴史散歩、史蹟めぐり、町めぐりを行い、郷土の埋もれた先人や史料を紹介する展覧会などを開催しました。
昭和30年代から50年代にかけて、郷土史家、学者たちが輪を大きく広げ切磋琢磨し、発表の場を充実させました。例えば、碩学日置謙師の流れをくみ藩政史全般の郷土史家山森青硯氏、加賀茶道史の研究にかけては右に出る人がいないとされた牧孝治氏、元内務省で神社神道を極め県内くまなく歩いて特に民俗史に金字塔を打ち立てた国立石川高専名誉教授の小倉学氏、名著『尾山神社誌』を編纂、執筆した北村魚泡洞氏ら錚々たる人たちが名を連ねました。
そして昭和43年、その年の研究発表の集大成として公に問うたのが「石川郷土史学会々誌」です。後世に自分の郷土史研究が残るとの矜持を胸に、健筆を競いました。活字文化がもてはやされていた古き良き時代です。最盛期には会員が150人ほどもいました。
平成から令和へ。石川県立図書館が新装オープンした令和5年、大きな転機を迎えました。発表の場を金沢市本多町の旧県立図書館から石引4丁目の北電本多の森庁舎2階の県立生涯学習センターまなびすとルームに代え、会長職もプロパーの役員から選出することになりました。県教委には引き続き多大なご協力ご支援を賜りますが、今後へ向けては組織としての自立を図る方針です。
本、雑誌、新聞といった活字文化はだんだん肩身を狭くしています。IT全盛の世となりました。石川郷土史学会も13年前から活動をリアルタイムに伝えるブログ「石川郷土史学会」を発信してまいりました。これに加えて、「石川郷土史学会」の歴史と現在の全容を伝えるため、創立73周年を迎えて新たにホームページも開設し、マルチメディアで今後も発信して参ります。
北國新聞文化センターと提携した特別講座「ふるさとの昭和100年」「金沢城と兼六園」も今年度から始まりました。受講者多数で好評裏に推移しています。